意味の広がりや違いを感じよう!
日本で広く使われている外来語には、フランス語由来のものが少なくありません。
外来語があることでフランス語の単語が覚えやすくなる反面、本来の意味が抜け落ちたり、変わってしまうことすらあります。
外来語・元の単語の両方を知って、意味の広がりや違いを感じてください。
第17回目は、「ノート」です。
日本語の「ノート」
「ノート」に関しては、最初に1つお断りしておく必要があります。
日本語の「ノート」は英語由来で、「notebook」を短くしたものですよね?
子どもの頃から慣れ親しんできた言葉なので、日本語で「ノートとは何か?」を説明するのは難しいほどですが、ここでは仮に「筆記用の冊子」ということにしておきます(不自然ですが…)。
- ノート「筆記用の冊子」
フランス語の「note」
前述通り、日本語の「ノート」は英語の「notebook」から入った外来語です。
英語には「notebook」の元になった単語「note」があり、その由来になったのはフランス語の「note」でした。
つまりフランス語の「note」が、英語を介して日本語の外来語「ノート」になったわけです。
ただしフランス語の「note」には、日本語の「ノート(筆記用の冊子)」という意味はありません。
日本語の「ノート」や英語の「notebook」に相当するフランス語は「cahier」なので、まったく別の言葉です。
では、フランス語の「note」にはどんな意味があるのかというと、「メモ・覚え書き」や、試験の点数などの「成績」、音楽用語の「音符・音」、「短い伝達文・連絡事項」という4種類が挙げられます。
これは「note」の元になったラテン語の単語が「しるし」という意味だったので、そこから派生する形で意味が広がったものです。
フランス語の「note」の使い方をまとめると、
- note①「メモ・覚え書き」
- note②「成績」
- note③「音符・音」
- note④「短い伝達文・連絡事項」
ということになります。
英語の「notebook」は、note①「メモ・覚え書き」を書くための「冊子」ということで、英語圏に入ってから作られた言葉です。
いろいろな「note」
「note」の使用例を挙げておきます。
- J’ai pris une note pour ne pas oublier.
(忘れないようにメモを取った)
→ note①「メモ・覚え書き」
- Elle a eu une bonne note en mathématiques.
(彼女は数学でよい点を取った)
→ note②「成績」
- Il a joué une fausse note au piano.
(彼はピアノで音を外した)
→ note③「音符・音」
- Le directeur a envoyé une note aux employés.
(社長が従業員に通達を出した)
→note④「短い伝達文・連絡事項」
などがあります。
なお、最後のフレーズの主語「le directeur」は、文脈によって「社長」「部長」「責任者」などと和訳されますが、ここでは「aux employés(従業員に)」があるので、「社長」としています。
この記事を音声で聞くなら
この記事は、ポッドキャストでも配信しています。
下のリンクのクリックで該当するエピソードに飛びますので、発音の確認などにお使いくださいね!

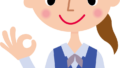

コメント