意味の広がりや違いを感じよう!
日本で広く使われている外来語には、フランス語由来のものが少なくありません。
外来語があることでフランス語の単語が覚えやすくなる反面、本来の意味が抜け落ちたり、変わってしまうことすらあります。
外来語・元の単語の両方を知って、意味の広がりや違いを感じてください。
第15回目は、「バー」です。
日本語の「バー」
「バー」に関しては、最初に1つお断りしておく必要があります。
日本語の「バー」は英語由来なので、「bar」と表記されているものもよく見かけますよね?
「バー」と言えば「お酒を飲む場所」という意味がまず思い浮かびます。
でもその他にも、「チョコバー」「シリアルバー」「エナジーバー」などと呼ばれる棒状の食品があります。
また、バレエなどで使われる手すりも「バー」と呼ばれます。
そして近年では、「バーコード」などに代表される技術用語としても使われています。
- バー①「お酒を飲む場所」
- バー②「(棒状の)食べもの」
- バー③「バレエなどで使われる手すり」
- バー④「(棒状の)技術用語」
フランス語の「barre」
前述通り、日本語の「バー」は英語の「bar」から入った外来語ですが、英語の「bar」の由来になったのはフランス語の「barre」でした。
ただし現在のフランスには英語の「bar」が逆輸入されて入り、外来語として使われています。
元の「barre」と英語由来の「bar」が、仲良く共存しているのです。
「barre」の本来の意味は「棒」「横棒」なのですが、それがカゴや檻などの「格子」や「柵」という意味にもなりました。
棒状の運動器具の名前にもなっています。
日本語の「バー」の意味の1つでもある「バレエなどで使われる手すり」はもちろん、鉄棒などにも「barre」が使われます。
そして「横棒を渡した状態」が転じて「障害」や「基準」という比ゆ的な意味も持つようになり、さらには「横棒を渡して仕切られた状態」から司法関係の用語としても使われるようになったのです。
フランス語の「barre」の使い方をまとめると、
- barre①「棒」「横棒」
- barre②「格子」「柵」
- barre③「棒状の運動器具の名前」
- barre④「障害」「基準」
- barre⑤「司法関係用語」
ということになります。
フランス語の「bar」
さて、ここからは英語そのものではなく、英語由来の外来語である、フランス語としての「bar」をご紹介します。
そもそもフランス語の「barre」にはなく、英語になって初めて広がった意味である「お酒を飲む場所」が、フランス語の「bar」の中心的な意味です。
そしてこうしたお酒を飲む場所にある「カウンター」という意味にもなりました。
お店の中にあるものだけでなく、家具としての「カウンター」としても使われます。
フランス語の「bar」の使い方をまとめると、
- bar①「お酒を飲む場所」
- bar②「カウンター」
ということになります。
いろいろな「barre」と「bar」
「barre」と「bar」の使用例を挙げておきます。
- J’ai acheté une barre de chocolat.
(チョコバーを買った)
→ barre①「棒」「横棒」
- Elle travaille dans un bar à vin.
(彼女はワインバーで働いている)
→ bar①「お酒を飲む場所」
- Le prisonnier regarde à travers les barres de sa cellule.
(囚人は牢屋の鉄格子の向こうを見ている)
→ barre②「格子」「柵」
- L’équipe a passé la barre des 10 000 spectateurs.
(チームは観客1万人の壁を突破した)
→ barre④「障害」「基準」
などがあります。
意味が激変した理由
ところで、本来は「棒」「横棒」という意味の「barre」が英語圏に入り、なぜ「お酒を飲む場所」を表すようになったのか、不思議ですよね?
でもその理由は、少々拍子抜けしてしまうほど、単純なモノでした。
お酒を提供する「店側と客側の境に横棒を渡して仕切りにしたから」だというのです。
元は境界線として渡した横棒でしたが、それがカウンターとして使われて「お酒を飲む場所」の象徴になり、場所の名前にもなったということです。
そしてさらに奇妙なのは、barre⑤「司法関係用語」でも、同じ理由で意味の広がりがあったということです。
こちらも古い法廷で、裁判官・陪審員と被告や証人を分けるために「barre(横棒)」を渡して仕切り を作っていました。
この「barre」はまさに酒場のカウンターと同じで、「ここから先は立ち入り禁止」という境界線の役割だったとか。
酒場と法廷…あまりにも違う場所なのに、同じ理由で意味が広がったのは、やはり不思議です!
この記事を音声で聞くなら
この記事は、ポッドキャストでも配信しています。
下のリンクのクリックで該当するエピソードに飛びますので、発音の確認などにお使いくださいね!

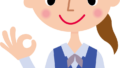

コメント