意味の広がりや違いを感じよう!
日本で広く使われている外来語には、フランス語由来のものが少なくありません。
外来語があることでフランス語の単語が覚えやすくなる反面、本来の意味が抜け落ちたり、変わってしまうことすらあります。
外来語・元の単語の両方を知って、意味の広がりや違いを感じてください。
第10回目は、「デッサン」です。
日本語の「デッサン」
日本語の「デッサン」は美術用語としてフランス語から入った言葉です。
そのため、この外来語が使われるのは、美術の文脈の中に限定されます。
「デッサン」と言えば、陰影や形を正確に描写するための、鉛筆などによる「素描」、つまり写実的なスケッチなどのことです。
- デッサン「素描・写実的なスケッチなど」
フランス語の「dessin」
フランス語の「dessin」にも「素描」などの意味がありますが、それは「dessin」という言葉のごく限られた一部の意味にすぎません。
なぜなら「dessin」には、「線で描かれた、文字以外のほぼすべての二次元画」といった幅広い意味があるからです。
日本語の「デッサン」にはない意味としては、例えば「子どもの描いたお絵描き」が挙げられます。
外来語の「デッサン」の場合は、鉛筆もしくはペンなどによる白黒のイメージが強いものです。
でもフランス語では、色鉛筆やクレヨンなどを使った色彩豊かな絵であっても、そしてそれが画家や美術専攻の学生などでない、小さな子どもによるものであっても、線で描かれた「線描」なら「dessin」と呼ぶのです。
そして「dessin」の意味する「線で描かれた、文字以外のほぼすべての二次元画」の中には、さらに「図形」や「図面」なども含まれます。
日本語の「デッサン」にどうしてもついて回る、美術・芸術のイメージからは程遠いような、機械工学の設計図なども、フランス語だと「dessin」です。
フランス語の「dessin」の使い方をまとめると、
- dessin①「素描・スケッチなど」
- dessin②「(子どもの)お絵描き」「線描」
- dessin③「図形・図面など」
ということになります。
いろいろな「dessin」
「dessin」の例文を挙げておきます。
- Mon fils a fait un joli dessin.
(息子がきれいな絵を描いた)
→ dessin②「(子どもの)お絵描き」「線描」
- L’architecte a présenté le dessin du bâtiment.
(建築家が建物の設計図を提示した)
→ dessin③「図形・図面など」
などがあります。
絵画との違い
日本語の「デッサン」とは、比較にならないほどいろいろな意味を持つ「dessin」ですが、フランス語には絵画を表す「peinture」という言葉もあります。
では、この2つの違いはというと、線が主役なら「dessin」、色が主役なら「peinture」であると言えます。
かなりざっくりとした言い方ですが、これこそがフランス人ネイティブの持つ感覚なのです。
そのため、子どもの描いたお絵描きすべてが「dessin」になるとは限りません。
小さな子どもは色鉛筆やクレヨンなどで「線による絵」を描くことが多いので、こうした作品は「dessin」ですが、少し大きくなって絵の具を使ったり、もしくはクレヨンなどだけでも「色が主体になった絵」であれば、その作品は「peinture」なのです。
なお、いろいろな画材を使って描いた絵であっても、線が主役なら「dessin」です。
そして線があったとしても、それは下描きか補足部分で、色が主役なら「peinture」ということになります。
ただし「dessin」の意味するのは「線で描かれた、文字以外のほぼすべての二次元画」です。
文字が主役の書道などは他の単語になり、「dessin」や「peinture」ではありません。
この記事を音声で聞くなら
この記事は、ポッドキャストでも配信しています。
下のリンクのクリックで該当するエピソードに飛びますので、発音の確認などにお使いくださいね!

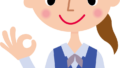

コメント